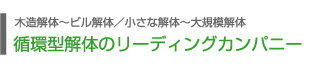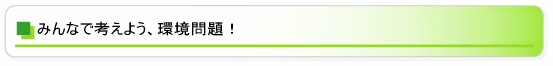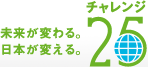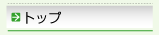
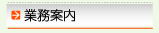
 解体の流れ、種類 解体の流れ、種類
 アスベスト処理 アスベスト処理
誰でもわかる「解体」
 解体現場編 解体現場編
 解体事務所編 解体事務所編
みんなで考えよう
環境問題
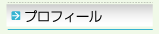
 概要 概要
 保有免許 保有免許
 加入団体 加入団体
 保有重機 保有重機
 工事履歴 工事履歴
 採用情報 採用情報
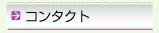
 お問合せ お問合せ
 プライバシー保護規定 プライバシー保護規定
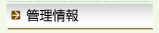
 リンク集 リンク集
 サイトマップ サイトマップ
 サイト運営規定 サイト運営規定
|
 |
|
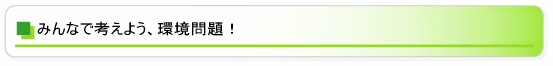
みんなで考えよう環境問題 > エネルギー白書2013 > わが国の原油自給率
|
| エネルギー白書2013 |
[ も く じ ]
・わが国の原油自給率(2013年)
・アジア産油国の石油需給(2013年)
・全国の原子力発電所の運転状況
・福島原子力発電所1~4号機の廃止措置に向けた中長期ロードマップ
・非難指示区域と警戒区域
・日本のエネルギー基本計画
■わが国の原油自給率(2013年)
我が国における一次エネルギーとしての石油の供給は、オイルショックを契機とした石油代替政策や省エネルギー政策の推進により減少しましたが、1980年代後半には原油価格の下落に伴って増加に転じました。1990年代半ば以降は、石油代替エネルギー利用の進展等により減少基調で推移しました。
我が国の原油自給率12は2011年度で0.4%であり、新潟県、秋田県及び北海道に主要な油田が存在しています。このように自給率が低いため、我が国は2011年度において原油の99.6%を海外からの輸入に依存しており、輸入先も中東地域が8割以上を占めました。2011年のアメリカの中東依存度13は20.5%、欧州OECDは21.6%であり、我が国の中東依存度は諸外国と比べて高くなっています。2011年度の輸入先を国別にみますと、サウジアラビアが31.1%でトップにあり、以下、アラブ首長国連邦(22.5%)、カタール(10.2%)、イラン(7.8%)の順となりました。
我が国は、二度のオイルショックの経験から原油輸入先の多角化を図り、中国やインドネシアからの原油輸入を増やし、1967年に91.2%であった中東地域からの輸入の割合を1987年には67.9%まで低下させました。しかし、近年、我が国の中東依存度は再び上昇し、2009年度は89.5%と非常に高くなりました。2011年度は①震災による国内製油所が稼動停止したこと②原発停止による石油火力発電用の低硫黄原油の需要が増加し、中東域外からの原油輸入増加したこと等により2000年以来の低水準となりましたが、それでも85.1%という割合でした。
■アジア産油国の石油需給(2013年)
アジアの産油国について、石油需給の動向を見ると、アジア諸国で石油需要が増加し、これまで輸出していた原油を自国の需要に振り向けた結果、輸出向けが減少する傾向にあります。
|
図表、データは「資源エネルギー庁サイト」より引用
このページのトップへ
|
|
|